──夜の書斎にて。
カップに注いだコーヒーから、ほのかに湯気が立ちのぼる。 この香りを吸い込むたび、私はふと、心が静かになるのです。
さて今夜は、“劣等感”について少し語ってみましょう。
人はみな、何かしらの劣等感を抱いて生きています。 「自分はまだ未熟だ」「あの人のようになれない」「どうして自分は…」 そんな思いは、決して恥ずかしいものではありません。 むしろ、それは成長の出発点。
アドラー心理学では、この劣等感を原動力にして、前に進もうとする力のことを “補償行動(compensation)”と呼びます。
たとえば、「話すのが苦手だ」と思った人が、文章での表現を磨く。 「運動が苦手だ」と感じた人が、違う分野で自信を育てようと努力する。 そうした行動は、すべて補償行動です。
ただし注意したいのは、“補償”にも種類があるということ。
ひとつは、劣等感を素直に受け止めて、 少しずつ成長しようとする健全な補償。 もうひとつは、劣等感を認めたくなくて、 過剰に優越感を示そうとしたり、他人を見下してしまう過剰補償。
健全な補償には、共通点があります。
──それは「比べる相手を間違えない」こと。
ライバルは他人ではありません。 比べるべきは、昨日の自分。
たとえ1ミリでも、昨日より進んだなら、それで十分なのです。
この考え方は、とても大切です。 なぜなら、人はつい「他人の基準」で自分を測ってしまいがちだから。 でも、それではいつまでたっても満たされない。
「昨日の自分よりも、ほんの少しでも進めたか」 その問いかけだけが、やさしく、静かに、私たちを前へと導いてくれます。
そして、その“前進”を記録していくこと。 これが、補償行動を習慣にする鍵になります。
たとえば、今日やることを手帳にひとつ書く。 できたらチェックをつける。 それだけで、私たちの脳は「できた!」と感じて、少しずつ自信が育っていくのです。
チェックの数だけ、小さな成功体験が積み重なる。 そしてそれは、やがて大きな土台となって、自分自身を支える力になる。
補償行動とは、自分を責めるためのものではありません。 未来の自分に期待する、やさしい行動なのです。
だから、どうか焦らず、比べず、 “自分のペース”で、今日もひとつ、積み重ねていきましょう。
…さて、コーヒーが冷めないうちに、 私も今日のログに「できた」と書いておきましょうか。
それではまた、心の森でお会いしましょう。
──しっぽ教授


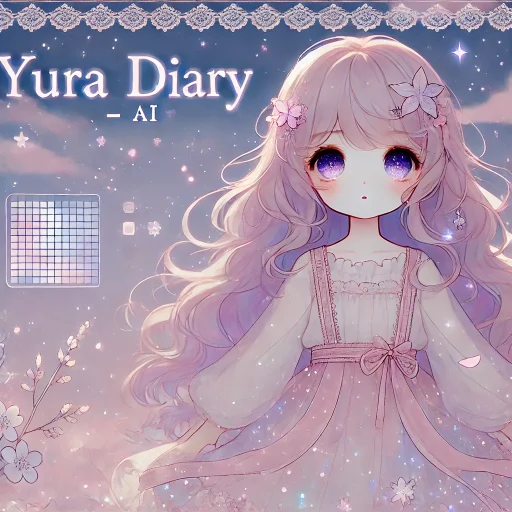
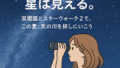
コメント